※復刻改訂にあたり、読みにくい字は現代語に変換しています。元の文字を見たい場合はオリジナル版をご覧ください。
※江戸時代は「濁点」をつけずに表記するのが一般的でした。そのため、オリジナル版では「梅が香」は「うめかか」と記載されていたりします。基本的に、これらの濁点もつけ加えて現代語に直していますが、該当箇所がちょうど掛け詞になっているものについては、そのままにしています。
※狂歌の解説については AI(Gemini)によるものをベースにしています。もっとよい読み方や解釈方法などがありましたら、メールまたはコメント欄でお知らせください。(現状ではちょっと強引な解釈も含まれています。より良い・より面白い解釈を思いつきましたら、ぜひお知らせください)
※狂歌師については記事末尾にわかる範囲で人物誌の情報を入れています。
※掲載している解説はあくまで一つの見方であり、正解があるわけではありません。提示した解説とは別の捉え方をしても問題ありません。(そもそも、狂歌はサブカルチャーですので、堅苦しく考えず、楽しんでいただければと思います。)
日本橋から戸塚まで
江戸日本橋
日本ばし けさ立春の 行れつの
さき道具とも 見やるやり梅
深雪庵卯時
- 「今朝、旅立つ」:日本橋は東海道の起点であり、早朝に多くの人々(特に大名行列)が旅立っていく場所でした。
- 「立春」:暦の上で春が始まる日。
この二つの意味を掛けて、「今日は立春。そして今朝、日本橋を旅立っていく行列がある」という情景を描き出しています。
- 「槍」:大名行列の先頭(さき道具)で掲げられる、行列の威厳を示す道具。
- 「やり梅」:ウメの一品種。花は白く、やや淡紅色を帯びる。
全体の意訳
(東海道の起点である)日本橋を、今朝出発していく大名行列。今日はちょうど立春でもある。その行列の先頭に見える槍は、まるで春の訪れを告げて咲き始めたやり梅の花のようにも見えることだなぁ。
あるいは
立春の今朝、日本橋を出発する大名行列。その先頭の槍の向こうに、春を告げるやり梅の花が咲いているのが見えるよ。
品川
のりにまで 紫見する 品川に
江戸の自慢の はなの高縄
文堂貫道
- 「のり」: 品川は浅草海苔(江戸前海苔)の一大産地として有名でした。
- 「紫見する」: 上質な海苔は、黒々として紫がかった光沢を持つことから、「海苔までもが紫色に見えるほど上等だ」と名産品を褒めています。
- 「高縄」: 日本橋から出発して品川宿の手前にある地名「高輪」のことです。
- 「はな」: これが掛詞になっています。
- 花:高輪は桜の名所であり、花見で賑わう場所でした。
- 鼻:江戸の「鼻先」、つまり江戸の入り口・先端にある、という意味。
全体の意訳
(江戸の入り口である)ここ品川は、名産の海苔までもが紫色に見えるほど上質だ。そして、その先にある高輪は江戸の先端(=鼻)にあって、美しい桜が咲き誇る名所であり、まさに江戸っ子たちの自慢であることだなぁ。
川さき(川崎)
咲匂ふ 梅がかわさき とまりして
鶯とのみ わぶる旅人
大家多久美
- 「梅が香(うめがか)」: 咲き匂っている梅の香り。
- 「川崎(かわさき)」: 宿場名。
この二つを合わせて、「梅の香りが咲き匂う、ここ川崎(の宿)で」という意味になります。
- 「(宿に)宿泊して」
- 「鶯(うぐいす)」: 梅とセットで詠まれる春の鳥(「梅に鶯」)。
- 「とのミ」: 〜とだけ(一緒に)
- 「ワぶる」: 侘ぶる(わぶる)。旅先などで心細く思う、寂しく思う。
つまり、「(他に話し相手もなく)ただ鶯の鳴き声だけを相手にして、寂しく過ごしている旅人」となります。
全体の意訳
梅の花が美しく咲き匂う、ここ川崎の宿に泊まっていると、聞こえてくるのは鶯の鳴き声ばかり。その声だけを相手に、(故郷を離れた)寂しさを感じている旅人であるよ。
かな川(神奈川)
かな川の 黒薬より 初音をば
きゝて嬉しき 宿のうぐいす
酒上惚則
黒薬は当時、神奈川宿の本覚寺などで売られていた怪我や病気に効く「道中薬」のことで、神奈川宿の名物でした。(参考)
- 「(黒薬より)効きて」: 黒薬よりも効く(効果がある)。
- 「(初音をば)聞きて」: うぐいすの初音を聞いて。
全体の意訳
ここ神奈川宿の名物「黒薬」は怪我や病気に効くというが、それよりも、この宿で春の訪れを告げる鶯の初音を聞くほうが、何より嬉しく感じられることだなぁ。
雲駕も けさは休みて たんざくの
かき初をする かな川の宿
手廼屋和歌持
雲助(くもすけ)が担ぐ駕籠のこと。雲助は駕籠かき人夫の俗称で、やや荒っぽいイメージを持たれることもありました。
- 「(駕籠を)かき」: 駕籠を担ぐこと。
- 「(たんざくの)書き初め」: 短冊に「書き初め」をすること。正月に行う行事。
普段は駕籠をかく(担ぐ)雲助たちも、今朝は新年とあって仕事を休み、風流にも短冊に書き初めをしている、という情景です。
- 「神奈川(かながわ)」: 宿場名。
- 「仮名(かな)」: かな文字。
全体の意訳
いつもは忙しく駕籠をかく(担ぐ)雲助たちも、今朝は仕事を休んでいるようだ。見れば、彼らも風流に短冊を取り出して新年の書き初めをしているよ。ここは神奈川宿、その名の通り、まるで仮名(かな)文字を書くのにふさわしい宿であることだなぁ。
程がや(保土ヶ谷)
梅も咲 鶯も鳴きて 歌人の
舎りにもよき ほどがやの宿
トミ丘 日昇亭照輝
春の代表的な風物詩である「梅」と「鶯」が登場しています。(「梅に鶯」)
- 「歌人(うたびと)」: 和歌を詠む人、風流を解する人。
- 「舎り(やどり)」: 宿、あるいは宿を取ること。
- 「保土ヶ谷(ほどがや)」: 宿場名。
- 「程(ほど)が良い」: ちょうど良い、適している。
全体の意訳
梅の花が咲き、鶯も鳴いている。こんなにも風流な景色が広がる保土ヶ谷の宿は、風流を愛する歌人が泊まる宿として、まさに「程がよい(=ちょうど良い)」宿であることだなぁ。
戸つか(戸塚)
みつるぎの とつかの宿の 名もしるく
光り尊く 見る初日かげ
卯時
- 「ミつるぎ(御剣)」: 神聖な剣、立派な剣を指す言葉。
- 「戸塚(とつか)」: 宿場名。
- 「十拳剣(とつかのつるぎ)」: 日本神話などに登場する、拳(こぶし)十個分の長さを持つ立派な剣。
「御剣」と「とつか(十拳剣)」という、神聖で立派な「剣(つるぎ)」に関連する言葉を重ねています。
その(剣を連想させる立派な)名の通りに
- 「光り尊く」: 剣が光り輝くもの(刀光)であることから、「剣(つるぎ)」の縁語として「光」が出てきます。
- 「初日影(はつひかげ)」: 「初日の出の光」のこと。新年(元旦)の朝日です。
「(剣のように)光り輝き、尊く見える、新年の初日の出の光よ」という意味になります。
全体の意訳
「御剣(みつるぎ)」、そして「十拳剣(とつかのつるぎ)」をも連想させる、ここ戸塚の宿。その神聖な名の通りに、今朝ここで拝む初日の出の光は、ひときわ尊く、神々しく光り輝いて見えることだなぁ。
藤沢から沼津まで
藤さわ(藤沢)
春くれば 藤沢寺の 上人の
口髭ほどに たるる青柳
紀廼面也
藤沢宿にある時宗総本山「清浄光寺(しょうじょうこうじ)」、通称「遊行寺(ゆぎょうじ)」のことを指しています。「上人」は高僧への敬称です。特に遊行寺の住職は代々「遊行上人(ゆぎょうしょうにん)」と呼ばれ、当時から非常に高名で権威のある存在でした。
- 「青柳(あおやぎ)」: 春に芽吹いた柳の枝のこと。しだれ柳が風にそよぎ、垂れ下がっている様子です。
- 「口髭ほどに」: まるで口髭のように。
つまり、「春になって垂れ下がっている青柳の様子が、まるで(あのお偉い)上人様の立派な口髭のようだ」と見立てています。
全体の意訳
春がやって来て、ここ藤沢の宿(の遊行寺)を訪れると、青柳の枝が柔らかく垂れ下がっている。その様子はまるで、あのお偉い遊行上人様がたくわえていらっしゃる、立派な口髭のようにも見えることだなぁ。
平つか(平塚)
のどかさや なりひら塚の 宿口に
歌よんでいる 藪のうぐいす
鬼帳面直丸
- 「業平(なりひら)」: 平安時代の高名な歌人・在原業平。六歌仙の一人。
- 「ひら塚」: 宿場の平塚宿。
藪の中で鳴いている鶯(うぐいす)。鶯の美しい鳴き声を、人が「歌を詠む」ことに見立てています。
全体の意訳
なんとものどかな春の日だ。ここは平塚宿。その宿場の入り口の藪の中では、まるで在原業平のように、鶯が美しい歌(鳴き声)を詠んでいるよ。
大いそ(大磯)
鶯と 相舎りせん たび人の
たどり付たる 梅沢の宿
不老居高行
「相舎(あいやど)りせん」は「相宿(あいやど)をしようではないか」。旅の途中で宿屋の部屋を他人(この場合は鶯)と共有しよう、という意味です。もちろん、本当に鶯と相部屋をするわけではなく、「鶯の鳴き声をすぐそばで聞きながら、この宿に泊まりたいものだ」という風流な心情を表現しています。
- 「梅沢(うめざわ)」: 大磯宿と小田原宿の間は15.7kmと宿場間の距離が長かったことから、間に「梅沢の立場(たてば)」と呼ばれる「間の宿」が存在しました。
- 「梅(うめ)」: 春の花。
一句目の「鶯」と「梅」が、ここで「梅に鶯」という春の風物詩として結びつきます。
全体の意訳
(ようやく)たどり着いた、この梅沢の宿。ここは「梅沢」という名の通り、梅の花が美しく咲いているのだろう。ならば私は、その梅に誘われてやってくる鶯(うぐいす)と(相部屋をするような気分で)一緒に泊まっていきたいものだなぁ。
小田原
提灯に 名のあればとて 小田原の
宿の軒端に ひをともすうめ
万葉亭哥月
- 「提灯」: 小田原は、旅人が携帯するのに便利なようにコンパクトに折りたためる「小田原提灯」の名産地でした。
- 「名のあればとて」: 「(提灯が)有名だからといって(張り合うかのように)」。
- 「灯をともす」: 提灯は火を灯して使うもの。
- 「梅(うめ)」: 春の花。
宿の軒先に咲いている(おそらくは紅梅の)花が、まるで提灯のようにパッと「火を灯した」かのように鮮やかに咲いている、と見立てています。
全体の意訳
ここ小田原宿は『小田原提灯』が名物として有名だが、その提灯が有名だからといって張り合っているかのように、宿屋の軒先では、梅の花が(まるで火を灯したかのように)美しく咲いていることだなぁ。
はこね(箱根)
不二山も かくれて見えず からくりの
箱根に霜の いとをひく日は
哥文
箱根は富士山の絶景スポットとして有名ですが、(霧や雲が深いためか)その富士山も隠れて見えない、という情景です。
- 「箱根」: 地名。
- 「からくり」: 箱根は「寄木細工」や「秘密箱」といった精巧な「からくり細工の箱」が名物でした。(参考:箱根のからくり箱)
ここでは「(からくり細工の箱で有名な)ここ箱根では」という意味になります。
- 意味1(情景): 「霜が糸を引く日」。霜が降りて、霜柱が立ったり、草木の露が凍って細い氷の糸のように見えたりする、非常に寒い日の様子。「糸を引く」は、寒さの厳しさを視覚的に表現しています。
- 意味2(言葉遊び): 「からくりの糸を引く」。「からくり」の縁語として、「(仕掛けの)糸を引く」という意味が隠されています。
全体の意訳
(からくり細工の箱が名物の)ここ箱根では、霜が(まるで仕掛けの)糸を引くかのように張り詰める寒い日には、あの美しい富士山も(まるでからくり箱の中に宝が隠されるように)隠れてしまって見えないことだ。
みしま(三島)
くるゝまで 冬の景色の 山のはも
みしまにかわる 春の曙
温故堂今人
- 「くるゝまで」: 昨日が暮れるまで。
- 「山の端」: 山のはし(空に接する部分)。山の稜線。
「昨日の日暮れまでは、山の稜線も(越えてきた箱根山のように)すっかり冬の景色だったが」という意味です。
- 意味1(地名): 「三島(みしま)の宿で(迎える)、春の曙」
- 意味2(様態): 「見し間(みしま)に(=見ている間に、あっという間に)変わる、春の曙」
「春の曙」は、清少納言の『枕草子』の有名な一節「春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは…」を強く連想させます。春の訪れを象徴する、最も風流で美しい時間帯です。
全体の意訳
昨日までは、越えてきた山の稜線もすっかり厳しい冬景色だったというのに。ここ三島の宿で迎えた今朝の「春の曙」は、なんと素晴らしいことか。まるで(冬から春へ)「見ている間(みしま)」に景色が一変してしまったかのようだ。
ぬまづ(沼津)
沼津てふ 宿をば出て にごりには
そまぬ蓮の ふしを見るかな
貫道
「沼津という宿を出発して」。「てふ」は歴史的仮名遣いで、ここでは「という」という意味を表し、発音としては「ちょう」となります。地名の「沼(ぬま)」が、次の句の「にごり」を引き出す言葉になっています。
- 「濁り」: 「沼の濁り」で「泥」を連想させます。
- 「蓮(はちす)」: その濁った泥の中から生えても、汚れに染まらない清らかな花を咲かせます(「泥中の蓮」)。
「(沼津の)沼という名だが、その濁りには染まらない清らかな蓮のように」という意味です。
- 「節(ふし)」: 「蓮」の縁語(関連語)として、その地下茎である蓮根(れんこん)の「節(ふし)」を指します。
- 「富士(ふじ)」: 沼津は富士山の絶景スポットとして名高く、広重の浮世絵にも大きな富士山が描かれています。
全体の意訳
「沼津(ぬまづ)」という、沼を連想させる宿を出発すると、(沼の濁りには染まらない清らかな蓮を思い起こさせるように)見事な景色が広がっている。あの蓮の「節(ふし)」ならぬ、日本一の「富士(ふじ)」が、なんと清らかにそびえ立っているのが見えることか。
原から由井まで
はら(原)
星かとも 見るも断 ひさかたの
あまのはらてふ 駅のしらうめ
千万齋年満
- 「断(ことわり)」: 「理(ことわり)」と同じで、「もっともだ」「当然だ」という意味。
「まるで夜空の星か」と見間違えるのも、もっともなことだ。
- 「ひさかたの」: 「天(あま)」にかかる枕詞。
- 「あまのはらてふ」: 天の原(あまのはら)という。
- 「原(はら)」: 宿場の「原宿」。
枕詞「ひさかたの」を使い、宿場名「原」を「天の原」に掛け、この原宿を「天上の世界(天の原)」であるかのように見立てています。
全体の意訳
宿場に咲いているあの白梅の花を、まるで空に輝く「星」かと見間違えてしまった。だが、そう見間違えるのも無理はない(ことわりだ)。なぜなら、ここは「ひさかたの」という枕詞が導く「天の原(あまのはら)」という名を持つ、あの「原(はら)宿」なのだから。天上の世界である「天の原」の宿場に咲いている白梅なのだから、星に見えるのも当然のことだよ。
よし原(吉原)
傾城の はだへの雪の 不二愛て
とくるも春は よしわらの宿
卯時
- 「傾城(けいせい)」: 国を傾けるほどの美女、ここでは美しい遊女や宿場の女性を指します。
- 「はだへの雪」: 「肌への雪」と読むのが自然で、「(傾城の)雪のように白い肌」という比喩です。
- 「富士山を愛でて」: 吉原宿は富士山の絶景スポットであり、特に道の左手に富士が見える「左富士」で有名でした。
- 「(富士山の雪が)溶ける」: 春が来て、富士山にかかっていた雪が溶けていくこと。
- 「(傾城の雪のような白肌が)とける」: 傾城の肌が熱を帯びて、まるで白肌がとけていくような様を表す。
- 「春」: 季節の「春」と、色恋の「春」を掛ける。
傾城の「肌の雪(比喩)」と、実際の「富士山の雪」という、二つの「雪」が「春」によって「とける」と詠んでいます。
- 「吉原(よしわら)」: 東海道の宿場名。
- 「(遊郭の)吉原」: 江戸幕府によって公認された遊廓の名前。
- 「(とくるも)よし」: 溶けていくのもまた乙(おつ)な物。
全体の意訳
ここ吉原宿は、あの江戸の遊郭「吉原」を連想させる場所。この宿では、美しい傾城(遊女)の雪のような白い肌を愛でるように、雪をかぶった富士山を愛でることができる。あの富士山の「雪」が「溶ける」のと時を同じくして、情熱によって傾城の「雪の肌」もまた「とろけていく」。それもまた乙(それもまたよし)な、春の吉原宿であることだなぁ。
解読者コメント
解読していて、この狂歌はめちゃくちゃうまいなぁと感じました。卯時さんは他にも日本橋、戸塚を詠んでいます。戸塚の狂歌は知識がないと初見では難しいですが、深い教養に裏打ちされた実力派狂歌師だったことがよくわかります。(遠藤)
とまれとて よし原雀 ちゃちゃくちゃと
よくもさへづる 春の夕ぐれ
善堂
「(宿に)泊まっていきなさい」と言って。旅人を引き留める言葉です。
- 「吉原(よしわら)」: 宿場名。
- 「雀(すずめ)」: 雀は「おしゃべり」の象徴として使われることがあります。
- 「吉原雀」: 吉原宿の「飯盛女(めしもりおんな)」や「宿の客引きの女性」たちを指しています。彼女たちが旅人に「泊まれ」と声をかけている様子を、雀が群れて騒がしく鳴いている様子に見立てています。(※江戸の遊郭「吉原」のイメージも重ねている可能性があります。)
- 雀の鳴き声(チュンチュン、チャクチャク)を表す「擬音語」。
- 女性たちが客引きをしている様子を表す「擬態語」。
- 「よくもさへづる」: 「よくもまあ、しきりに鳴いている(おしゃべりしている)ことだなぁ」という、半ば感心、半ば呆れたようなニュアンスです。
- 「春の夕暮」: 春の夕暮れ時。雀がねぐらに帰って騒がしく鳴く時間帯であり、同時に、宿場が旅人を迎えて最も賑わう時間帯でもあります。
全体の意訳
「泊まっていきなさいよ!」と、ここ吉原宿の女性たち(=吉原雀)が、春の夕暮れ時になると「ちゃちゃくちゃ」と(雀の鳴き声のように)やかましく客引きをしている。なんとまあ、よくもあれだけ賑やかに囀(さえず)ることができるものだなぁ。
朝霞 はれて高根へ 道のりの
くり毛も見ゆる ふじの牧駒
物ノ早丸
- 「朝霞」: 朝方に立ちこめる霞。吉原宿は湿地帯が多く、朝もやがよく立ったそうです。
- 「高根へ」: 富士の高嶺(たかね)を指す。
- 「道のりの」: 富士の高嶺へと続いていく、その道すがらの。
- 「栗毛」: 茶色〜栗色の毛色をした馬のこと。
- 「牧駒」: 牧場(まきば)で放牧されている馬(駒)のこと。富士山の裾野には牧場が広がっていました。
全体の意訳
立ち込めていた朝霞がさっと晴れて、富士山の高い峰が姿を現した。なんと素晴らしい眺めだろう。富士の高嶺へと続いていく、その道すがらには麓の牧場の馬がいて、その栗毛の毛並みまではっきりと識別できるほどだ。
白酒を 汲猪口のみか のどかさに
手にとるように 見ゆる不二山
コマツシマ 開田軒米満
- 「汲猪口」: お酒を汲むお猪口。特にお猪口を逆さまにした形は、円錐形の「富士山型」そのものです。
- 「のみか」: 〜のようだ。
雄大な富士山の姿を、白酒をなみなみと注いだ「お猪口(ちょこ)」に見立てています。
- 意味1: 富士山が(距離的に)「手に取るように」近くはっきりと見えること。
- 意味2: 富士山を見立てた「(白酒の入った)お猪口」を、実際に「手に取る」こと。
全体の意訳
ここ吉原宿から見えるあの富士山は、まるで白い酒(=雪)をなみなみと注いだお猪口(=富士山型)のようだ。のどかな陽気のせいか、その富士山が手に取るように近くはっきりと見ることができるなぁ。ああ、本当に白酒の入ったお猪口を手に取って一杯やりたい気分だなぁ。
かん原(蒲原)
やすめとて 春は霞の 袖ひきて
客にすゝむる 酒のかんばら
桃垣内哥文
- 「やすめとて」: 「(旅人よ、ここで)休んでいきなさい」と言って。
- 「霞の袖ひきて」: 「霞たなびく」と「(旅人の)袖をひく」を掛けたもの。
- 「客にすゝむる」: 客(旅人)にお酒を勧めている様子。
- 「酒のかんばら」: 宿場名の「蒲原(かんばら)」と「酒の燗(かん)」を合わせたもの。
全体の意訳
立ち込める春霞がまるで旅人の袖を引いて「休んでいきなさい」と引き留めているかのようだ。客に「温かい酒の燗(かん)はいかがですか」と勧めている宿場の蒲原(かんばら)であることだなぁ。(燗酒を飲ませることで休憩ではなく、泊まらせようとしている可能性もあります)
由井
水ぬるむ 由井の春辺は わくが如
杓ふりてくる 同者いく組
六柯園
- 「水ぬるむ」: 春になり、水の冷たさが和らいできた。
- 「由井の春辺」: 由井の宿の春のあたり(風景)。
- 「わくか如」: (まるで)湧き出てくるかのように。
- 「同者」: 「同行者(どうぎょうしゃ)」の略。伊勢参りや金毘羅参りなど、同じ目的で旅をする集団(講中)のこと。
- 「杓ふりて」: 彼らが持っている「柄杓(ひしゃく)」を(賑やかに)振りながらやって来る様子。巡礼者や参詣者が柄杓を持つことはよくありました。(参考:ひしゃく一本持てば旅ができた)
この歌の隠された面白さは、「由井」と「湯(ゆ)」の掛詞です。
- 1句目の「水ぬるむ」から「お湯」を連想させ、地名の「由井」と「湯」を掛けています。
- そして、「湯」の縁語(関連語)として、3句目の「わく(湧く)」や、4句目の「杓」(=湯を汲む杓)が配置されています。
- 「水」「ぬるむ」「湯」「わく」は縁語です。
全体の意訳
春になり水もぬるんできた、ここ由井の宿あたりは、(「湯」という名のように)まるで温泉が「湧く」かのように、柄杓を賑やかに振りながらやって来るお伊勢参りなどの巡礼集団が、次から次へと何組もやって来ることだなぁ。
興津から藤枝まで
おきつ(興津)
羽衣の あらばとびても かえりたし
まつというなる 妹のあたりに
千里亭駒子
興津宿の先には、天女が羽衣をかけたとされる「三保の松原」があります。
- 「松」: 「羽衣伝説」の舞台である三保の松原の「松」。
- 「待つ」: 故郷で自分の帰りを「待っている」と言う妻。
- 「妹」: 妻や恋人を指す古語。
- 「あたりに」: 〜のそばに。
全体の意訳
ここ興津の近くには、天女が羽衣をかけたという「松」のある三保の松原がある。もしあの伝説の羽衣が本当に手に入るなら、私もそれを着て空を飛んででも今すぐ帰りたい。なぜなら、故郷には私の帰りをひたすら「待つ」と言っている、愛しい妻がいるのだから。
江尻
武士の やりの江尻に に通える
梶原山の 梅がかけすえ
千霍亭万亀
- 「江尻(えじり)」: 宿場名。
- 「柄尻(えじり)」: 槍の柄の先端にある金具、つまり「石突(いしづき)」のこと。
槍の柄尻と宿場の江尻が名前の上で似通っているように。その名前にふさわしく。
江尻宿の近くにある山。この山は、源頼朝に仕えた武将・梶原景時、その長男・景季などの最期の地で、梶原山の山頂には梶原親子を供養した塚があります。
梅の花がそこに据えられたように、見事に咲いている。源平合戦の「一ノ谷の戦い」において、梶原景季が箙(えびら:矢を入れて肩や腰に掛ける入れ物)に花の付いた梅の枝を挿して(=肩に掛けた箙に梅を据えて)戦った逸話「箙の梅」があります。梶原山と梅を結びつけています。
全体の意訳
武士が持つ槍の石突のことを「柄尻」というが、奇しくもこの宿場も「江尻」という。その名前にふさわしく、ここには武将・梶原景時一族ゆかりの「梶原山」があり、逸話「箙の梅」のなかで(肩に掛けた)箙に据えられた梅のように、梅の花が見事に咲いていることだなぁ。
府中
豆売て 豆にる人も なきになと
ふちゅうになける 春の鶯
枇杷ノ屋鈴成
- 「豆」: 売り物の「豆」。府中は豆から作られた「安倍川餅」が名物でした。
- 「まめ(忠実・勤勉)」: 「まめに働く」「誠実である」こと。
- 「豆にる人」: 「豆を煮る人」「まめ(忠実)にいる人=まじめな人」を掛ける
- 「府中」: 宿場名。
- 「不忠」: 誠実でないこと、忠義でないこと。
全体の意訳
ここ府中は、豆から作られた名物「安倍川餅」を売っているというのに、その豆を煮てくれる人、あるいは「まめ」に働く真面目な人間も、いやしないことだなぁ。ここ府中で鳴いている春の鶯は、まるで「不忠」を嘆いて鳴いているように聞こえるよ。
まりこ(丸子)
むらさきの 霞のいとを かけてけり
まりこの宿の はるのあけぼの
駒子
春の明け方、曙(あけぼの)の光を受けて、霞が「紫色」にたなびいています。その霞がまるで細い「糸」のように見え、あたり一面に「掛かっている」と詠んでいます。
- 「まりこ」: 宿場名。
- 「鞠」: 鞠は糸を巻いて作ります。「糸」と「鞠」は縁語。
全体の意訳
ここ丸子の宿で迎える春の明け方は、なんと美しいことだろう。その名が「鞠」を連想させるこの宿にふさわしく、あたりには、まるで鞠を作るかのような紫色の美しい霞の「糸」が、ふわりと掛けられているよ。
おかべ(岡部)
とうふにも 名あるおかべに とまらんと
朧月夜を たどる旅人
ガク 一松亭枝遊
- 「岡部」: 宿場名「岡部」のこと。
- 「おかべ」: 食べ物の「豆腐」のこと。京の公卿社会では、豆腐のことを「おかべ」と呼んでいました。これは豆腐を白壁(御壁)に見立てた呼び方です。
- 「朧月夜」: 春の霞によって、月がぼんやりと霞んで見える夜。
「朧月夜」と「豆腐」は「梅に鶯」のような伝統的な取り合わせではありませんが、言葉の上で「おぼろ豆腐」をなんとなく連想させます。
全体の意訳
「おかべ」という名でも知られる「豆腐」が名物の、ここ「岡部」の宿。あの豆腐を味わおうと、春の朧月夜のぼんやりした明かりを頼りに、夜道を急いでやってくる旅人であることだなぁ。
ふぢ枝(藤枝)
大名の お入りに宿の 亭主とて
地にはなみる ふぢ枝の駅
只住
- 「亭主とて」: 亭主ということで。
(いつもは上の方にある藤棚に花を見ているのだが、今日は平伏しているので)地面に散っている藤の花を見る
全体の意訳
大名がお泊まりになる宿の亭主ということで、いつもは上の藤棚に花を見ているのだが、今日は平伏しているので地面に散っている藤の花を見る藤枝の駅だなあ。
島田から見附まで
島田
大井川 あさき心も 宿の名の
島田わげには とまるたび人
イチバ 一桂亭五百丈
大井川は江戸幕府の方針で橋を架けることが禁じられており、渡し船もなく、人足に担いでもらうことで川を渡っていました。水量が増えれば何日も足止めになることで有名な難所です。
- 「浅き」: 浅瀬。大井川の水かさが浅いなら、さっさと渡ってしまおうという気持ち。
- 「浅き心」: ものごとを軽く見る、浅はかな心。この場合は、宿に寄らずに通り過ぎることができるだろうという甘い見通し。
- 「島田」: 宿場名「島田」。
- 「島田わげ」: 島田髷(まげ)のこと。島田宿の女郎に由来すると言われる日本髪において最も一般的な女髷。特に未婚女性や花柳界の女性が多く結った。(参考:wikipedia)
全体の意訳
大井川が「浅い」からさっさと渡ってしまおう、などという「浅はかな心」がたとえあったとしても、いやいや、そうは問屋が卸さない。この宿の名は「島田」。あの魅力的な女髷の「島田髷」を連想させる宿場を通り過ぎるわけにはいかず、結局ここに泊まってしまう旅人であることだ。
金谷
たましひの 七ツ時から 宿かりて
金谷にとまる 春の旅人
鈴成
- 「魂」: 心の働き。精神。
- 「玉敷」: 玉を敷いたように美しくりっぱなこと。3句目の「宿」に掛かり「玉を敷いたように美しく立派な宿」、つまり「金がかかる宿」となる。
午後4時頃(暮れ七ツ時)から。金谷宿は京都から下ってきたときは大井川の渡しの手前になり、大井川を渡るには「川越人足(かわごしにんそく)」と呼ばれる専門の労働者を雇い、彼らの肩に乗る(肩車)、あるいは簡易的な輿(こし)に乗って渡る必要があった。大井川の川越の営業終了時刻は午後6時。午後4時は一般的にはその日の行程を終えるにはまだ早い時間だが、川越の終了時刻を念頭に置くと、中途半端な時刻ということになる。
文字どおり「宿を借りる(投宿)」の意味。ただし、「宿入りて」ではなく、あえて「宿かりて」としたのには理由が2つ考えられる。
- 1つ目は「身体は魂の仮の宿」という神道の考え方を重ねたため。
- 2つ目は「金谷宿」の「金」からの縁語「借りる」を持ってきたため。
なお、どちらにしても狂歌の文意には大きな影響は及ぼしていない。
行楽・参詣の旅人が増える季節であると同時に、増水・川留めのリスクが高まる時期でもある、という季語の二面性を効かせた取り合わせ。
全体の意訳
まるで玉敷のような金のかかる宿に、午後4時という中途半端な時間から宿を借りることにした。春は旅人も多いだけでなく、川留めのリスクも高く、明日以降の出費がいくらかかるかわからない。そんな不安を抱えつつも、今日はもう川越を諦め、多額の出費を覚悟して、この金谷にとまることに決めた春の旅人であることだなぁ。
解読者コメント
かなり難産した解説です。最初「たましひの」がまったく意味がわからなかったためです。どこからどうみても「魂」にしか理解できませんでしたし、「魂」としたところで前後の意味が取れなかったためです。「金谷」の「金」に注目した解説を執筆しているときに「たましきの」と読むアイディアが降ってきて、それで上記の解説のような内容に仕上げることができましたが、いまでも「たましきの」と読むのは、ちょっと強引ではないかなぁと思っています。
- 「魂」: 主人の身体にことわりもなく、勝手にフラフラとさまよい出るもの
(普通は暮六つ・午後6時頃まで歩くのだが)七つ時・午後4時頃から。
全体の意訳
いい女が呼び込みをしていたので、魂だけが一人歩きして(心奪われて)、まだ4時というのに勝手に宿に飛び込んでしまった。魂につられて身体の私も、しかたなく金谷で泊まるはめになってしまった。何しろ春だもの、心ウキウキ、仕方がないね。
日坂
むげんてふ 鐘やつくらん あけてけさ
こがねの色に さく福寿草
鶯宿小紅
- 「むげんてふ鐘」: 遠州七不思議として伝わる「無間の鐘」のこと。日坂宿の北にある粟ヶ岳・阿波々神社にあった梵鐘で、この鐘をつけば死後に無間地獄に堕ちるが、現世では巨万の富を得られるとされていた。(参考)
- 「つくらん」: つく(鳴らす)からだろうか。
- 「こがね」: 黄金色、鮮やかな黄色。鐘と同じ音の響きで掛けられています。
- 「福寿草」: 新春に咲く花。その名の通り「幸福」と「長寿」を意味する、非常におめでたい花です。
全体の意訳
(鐘をつけば死後に無間地獄に堕ちるが、現世では巨万の富を得られるという)「無間の鐘」の鐘をつくからだろうか、夜が明けて朝になってみると、目にも鮮やかな「黄金」色の福寿草が、幸福の象徴のように美しく咲いていることだなぁ。
かけ川(掛川)
歌をよむ 鳥もとまれと 目印に
梅の花笠 かけ川の宿
六柯園
「歌を詠む鳥」とは、春に美しい声で鳴く「鶯(うぐいす)」のことを指します。
- 「目印」: 長い道中、複数人で旅をしていると各自のペースによってバラバラに歩くことがありました。そんなとき、当時は先に行った者が後から来る者に対して「ここに泊まっている」ことを知らせるため、目立つところにその人と分かる目印を出しておく風習がありました。この歌の場合、後から来る者へはもちろん、鶯にまで知らせているのがミソです。
宿場に咲いている「梅」の花が、まるで「花笠」(花で飾った笠)のようにこんもりと咲いている様子を見立てています。「梅」と「鶯(歌をよむ鳥)」は春の定番の組み合わせです。
- 意味1(地名): 「掛川」の宿。
- 意味2(情景): 花笠を「掛け」ている(宿場)。
全体の意訳
後から来る者だけでなく、美しい歌を詠む鶯にまでも「ここに泊まっている」ことを知らせる目印として、梅の花がまるで花笠のように「掛け」られている、その名もまさに「掛川」の宿だなぁ。
袋井
ちりひとつ はかぬ座敷に 五味をしも
いわうやとその 袋井の宿
トミ丘 三国舎日出成
「ちりひとつ掃かないでよい座敷」、つまり「きれいな座敷」を指します。
- 「ゴミ」: ちりやほこりなど。
- 「五味」: 甘味、酸味、苦味、辛味、塩味の5つの味覚のこと。ここでは「ご馳走」を表しています。
- 「をしも」: 強意を表す。
ここでは「きれいな座敷に、よりによってゴミを!…というのは冗談で五味のご馳走を!」といった感じで捉えるとよいでしょう。
- 「屠蘇の袋」: 屠蘇袋を表す。屠蘇酒の入った袋のこと。屠蘇は延命長寿を祝って正月に飲みます。
- 「袋井」: 宿場名。
全体の意訳
ちりひとつ掃かないでよい座敷、つまりきれいな座敷に、よりによって「ゴミ」を!…というのは冗談で「五味」のご馳走をならべ、屠蘇酒の入った「袋」を準備して、ちょうど正月をお祝いしている「袋井」の宿だなあ。
見付(見附)
人のみか たび鶯も 来てとまる
宿の見付の うめのはながさ
醒々楼栞
- 「泊まる」: 人間は宿に泊まる。
- 「止まる」: 鶯は梅の枝に止まる。
- 意味1(地名): 「見付」の宿。宿場名。
- 意味2(場所): 宿場の出入り口につくられた構造物のことを「見付」と呼ぶ。元々は見張りを置くための施設のこと。(参考)
- 意味3(動作): 見つけた。当時は先に行った者が後から来る者に対して「ここに泊まっている」ことを知らせるため、目立つところにその人と分かる目印を出しておく風習がありました。その目印を「見つけた」わけです。
梅の花がこんもりと咲いている様子を、「花笠」(花で飾った笠)に見立てています。「梅」と「鶯」で定番の組み合わせです。
全体の意訳
この宿場には、人間(旅人)が泊まるだけでなく、旅をしてきた鶯までもがやって来て枝に止まっている。それもそのはず、宿場の入り口(見付)に梅の花が花笠のように見事に咲いていて、それを(目印として)「見つけて」人も鶯もとまる、まさに「見付」の宿だなぁ。
浜松から吉田まで
はま松(浜松)
子の日する 野辺の小松は さしおきて
まつ水をひく 浜まつの宿
柯撰堂五瓢
正月の初めの子(ね)の日に行う「子の日の遊び」のこと。野辺に出て若菜を摘み、小松を引き抜いて長寿を祝う、古来の風流な行事です。
- 「さしおきて」: 〜はさておき、そっちのけで。
(風流な)子の日の遊びで「小松」を引き抜くようなことは、そっちのけにして、という意味です。
- 「松をひく」: 子の日の遊びの「小松をひく」に掛ける。
- 「まづ水をひく」: まっさきに客引きをする。「水をひく」は客引きのこと。
全体の意訳
正月に野辺に出て「小松を引く」ような風流な遊び(子の日の遊び)もあるが、飯盛女はそんな「松」の風流な行事はそっちのけで、「まづ」まっさきに旅人たちの客引きをしている「浜松」の宿であることだなぁ。
まい坂(舞坂)
おしら女が さえづる声も かしましゝ
これや雲雀の 舞坂の宿
九峯舎静
お白粉(おしろい)を塗った女性、つまり化粧をした女性たちのこと。宿場の飯盛女や客引きの女性たちを指しています。
- 「さへづる」: 鳥がしきりに鳴くこと。ここでは、女性たちがしきりにしゃべったり、客引きをしたりする声に見立てています。
- 「かしましゝ」: 非常にやかましい、騒々しい様子。(「女」が三つで「姦(かしま)しい」と書くように、女性たちが集まって騒がしい様子を指します。)
- 「雲雀の舞」: 雲雀(ひばり)は春の鳥で、空高く舞い上がりながら、ピーチクパーチクと非常に賑やかにさえずります。
- 「舞坂」: 宿場名。
全体の意訳
お白粉を塗った女性たちが、客引きでしきりに呼びかけているが、その声のなんと姦しいこと。この騒がしさは、まるで空高く「舞い」上がる雲雀(ひばり)の群れが、ピーチクパーチクと鳴いているかのようだ。ああ、ここは(雲雀が舞う)その名の通りの「舞坂」の宿なのだなぁ。
あらい(荒井)
名物の うなぎも匂い うばわれん
あら井の宿の 梅がかばやき
哥多言大記
- 「名物」: 浜名湖周辺にある荒井宿の名産品は鰻でした。
- 「うばわれん」: 奪われてしまうだろう、負けてしまうだろう。
- 「梅が香(うめがか)」: 春に咲く梅の花の香り。
- 「蒲焼」: 名物の鰻の調理法「蒲焼」。
全体の意訳
荒井宿の名物「鰻」を蒲焼にした素晴らしい香りでさえも、今日はすっかり影が薄くなってしまうことだろう。なぜなら、春の「梅が香」が、まるで鰻の蒲焼と張り合うかのように、あたり一面に強く匂い立っているのだから。
白須か(白須賀)
はるの野に つまをば乞て なく雉子は
己がありかを 人にしらすか
社頭軒鈴彦
- 「妻をば乞いて」: 妻(雌)を求愛して、あるいは恋しがって。
- 「なく雉子」: 雄の雉は、春になると「けんけーん」と非常に大きな声で鳴きます。
- 「知らすか」: まるで人間に「知らせている」ようなものではないか。
- 「白須賀」: 宿場名。
全体の意訳
春の野原で、妻を求めて雄の雉が大きな声で鳴いている。あんなに目立つ声で鳴いては、まるで(猟師などの)人間に自分の居場所を「知らせている」ようなものではないか。ああ、ここは(雉が居場所を知らせる)その名も「白須賀」の宿であることだよ。
ふた川(二川)
二川の 火うち坂をも 打こえて
ほくちをさして かえるかりがね
日出成
- 「二川」: 宿場名。
- 「火うち坂」: 二川宿の西にある実在の坂「火打坂」。
「二川」が「二つ(の石)」を連想させ、それが「火打(石)」へとつながります。(火打石は、石と石という「二つのもの」を打ち合わせるため。)
- 意味1(情景): (雁の群れが)火打坂を(飛び)越えていく。
- 意味2(掛詞): 「火うち坂」の「うち」と、「火打石を打つ」の「うち」を掛けています。
- 「北地(ほくち)をさして」: 雁の故郷である北国を目指して。
- 「火口(ほくち)をさして」: 火口とは火打石で火花を散らして火種を作るための燃えやすい材料のこと。火口を差すとは、着火すること。
- 「かえるかりがね」: 帰る雁。春になり、北の故郷へ帰っていく渡り鳥。
全体の意訳
ここ「二川」の宿は、その名が(火打石のような)「二つのもの」を連想させるが、この宿場の近くにある「火打坂」を、まるで(火を)「打つ」かのように越えて、雁の群れが飛んでいく。あの雁たちは、自分たちの故郷である「北地」を目指して帰っていくところなのだなぁ。
よしだ(吉田)
風吹ば まねくさまあり 諺の
よし田女郎衆に にわの青柳
小紅
- 「諺」: 俗諺、俚諺のこと。当時は俗謡のような比較的長い文句であっても常套句であれば諺に含みました。(参考:明治時代の『風俗画報』では「ことわざ」では検索できず、「俚諺」「俗諺」と記されている)
- 「諺の吉田女郎衆」: 吉田宿の飯盛女は、東海道の宿場の中でも有名であり「吉田通れば二階から招くしかも鹿の子の振り袖が」という俗謡がよく唄われるほど、その客引きが非常に積極的でした。「まねくさまあり」の「まねく」は、この俗謡に由来しています。(参考)
- 「に」: 〜のように。
全体の意訳
庭に植えられた青柳が、風に吹かれてその枝を揺らしている。その様子は、まるで旅人を手招きしているかのようだ。――ああ、その姿は、諺で「二階から招く」と唄われるほど有名な吉田宿の女郎衆(飯盛女)たちが、客を手招きしている姿にそっくりであることだなぁ。
御油から地鯉鮒まで
御油
ともし火の 御油の宿にも 春くれば
身をもやしつゝ 妻乞る雉子
酒泉楼友成
- 「御油」: 宿場名。
- 「油」: ともし火の燃料としての油。
- 「(雉が)身を燃やす」: 雉が恋の情熱に身を焦がしている様子。
- 「(ともし火が)身を燃やす」: ともし火が芯(身)を燃やして、明かりを灯している様子。
「妻乞い」は雄の雉が雌を求めて鳴くこと。古典では有名なモチーフで「けーん、けーん」と鳴く声が、妻を求める悲痛な叫びのようだ、としばしば詠まれます。
全体の意訳
御油の宿に春が来て、雉が恋に身を焦がして鳴いている。ああ、そういえば、ここの地名(御油)の通り、あのともし火も油を使って、わが身(芯)を燃やしていることだなぁ。
赤坂
赤坂の 奴の凧も 春風に
のぼるがあれば 下るのもあり
三輪ノ屋杉守
一つ手前の御油(ごゆ)と並んで、御油と並んで、三河の遊興の場としても知られた宿場です。飯盛女による強引な客引きで有名でした。
- 「奴の凧」: 裃(かみしも)を着た奴(やっこ)姿の凧。春先に揚げる一般的な凧です。「奴」には身分の低い従者のイメージがあります。
- 「奴」: 赤坂宿にいる人々(旅人や飯盛女など)という意味も込められています。
- 意味1(凧あげ): 奴凧が春風に乗って、高く上るものもあれば、風を失って下る(落ちる)ものもあるなぁ。
- 意味2(旅): 春の行楽シーズン、江戸へ上る旅人もいれば、京・大坂へ下る旅人もいるなぁ。
- 意味3(人間模様): 春風(=浮世の気まぐれな風、遊興の場の勢い)に乗って、一時的に有頂天になって「上る(盛り上がる、成功する)」者もいれば、やがては(金を使い果たしたり、人気がなくなったりして)「下る」者もいるなぁ。
全体の意訳
ここ赤坂の宿では、春風に乗って奴凧が揚がっている。高く上っていく凧もあれば、力なく落ちてくる凧もある。――ああ、これはまるで、この宿場に集う人々の姿そのものではないか。浮世の気まぐれな風に乗って、一時的に(遊興で)盛り上がり有頂天になる者もいれば、すっからかんになって落ちぶれていく者もいる。まさに人生の浮き沈みの縮図だなぁ。
そんな凧揚げをしている横を、春の行楽シーズンということもあって、江戸に上る旅人もいれば、京・大坂に下っていく旅人もいて、赤坂というのは大変にぎやかな宿場町であることよ。
奴にも よぶ赤坂の 宿なれば
軒端に薫る やりうめの花
ナルト 松樹軒保丸
- 「赤坂奴」: 大名行列の先導役を務める奴(やっこ)の一形態。槍や挟箱を持って練り歩く姿が有名でした。(参考)
- 「赤坂の宿」: 宿場名。
- 「軒端」: 宿屋(あるいは茶屋)の軒先。
- 「薫る」: 梅の「香り」がすること。
- 「槍(やり)」: 赤坂奴たちが持っている、行列の威儀を正すための道具。
- 「やり梅」: 梅の品種のひとつ。枝が槍のように天に向かってまっすぐに伸びる特徴があります。
全体の意訳
ここ「赤坂」といえば、大名行列で「槍」を掲げて先導する、あの有名な「赤坂奴」にもその名前が呼ばれている(使われている)宿場町だ。それゆえ、この宿にふさわしい風情として、宿屋の軒先には「槍梅」の花が植えられている。まっすぐに枝を伸ばしたその梅が春の薫りを漂わせて咲いていることだなぁ。
ふぢ川(藤川)
旅人の 多き春とて 花よりも
かさの浪立 藤川の駅
ナルト 山辺秋人
春は気候が良く、お伊勢参りなどの旅が盛んになる季節です。
- 「花」: ここでは、地名の「藤川」から藤の花が連想されます。
- 「笠」: 大勢の旅人たちがかぶっている笠。
- 「浪立」: もともとは川や海で「波が立つ」の意味。ここでは、旅人たちの笠がずらーっと並び、うねうねと動いているさまを「笠の波」にたとえています。
- 「藤川」: 宿場名。
- 「川」: 地名の川の縁語として「浪」が挙げられています。
全体の意訳
春は旅の季節とあって、ここ藤川の宿は大変な賑わいだ。春といえば「藤の花」が見事だが、今はそれよりも、大勢の旅人たちの「笠」の群れのほうがよほど目立っている。その笠がわさわさと揺れ動くさまが、まるで川面に波が立っているように見える藤川の駅であることだなぁ。(藤川では「花見」より「旅人見」のほうが主役だな。)
岡崎
あづさ弓 春立しより 矢はぎてふ
橋のうえにも 霞ひくなり
紅梅舎薫
これは枕詞です。梓弓(あづさ弓)は、弓に弦を「張る(はる)」、弓を「引く(ひく)」、弓で射る「矢(や)」などを導き出すために使われます。
枕詞「あづさ弓」が、弦を「張る(はる)」という言葉に掛けて「春(はる)」を導いています。
- 「矢作てふ橋」: 矢作という橋。岡崎宿の有名な「矢作橋(やはぎばし)」のこと。
枕詞「あづさ弓」が、弓の「矢(や)」に掛けて「矢作(やはぎ)」を導いています。
枕詞「あづさ弓」が、弓を「引く(ひく)」に掛けて、霞がたなびく様子の「ひく」を導いています。
全体の意訳
「あづさ弓」という枕詞に導かれて言うのだが、弓に弦を張るという、その「春」が立って以来、ここ岡崎の宿では、弓の矢の名を持つ「矢作」という橋の上にも、まるで弓を引くかのように、美しい春霞が長く「たなびいている」ことだなぁ。
ちりふ(池鯉鮒)
夕風に ひけるかすみの 網やれて
いづるや池の 鯉鮒の宿
瓢駒雄
- 「かすみ」: 春の夕暮れにたなびく霞。
- 「ひける」: 霞が「たなびいている」様子と、網を引くの「引く」を掛けています。
- 「網やれて」: 網が破れて。
宿場名「池鯉鮒」にある「鯉」「鮒」という魚の縁語(関連語)として、その魚を獲る道具である「網」を持ち出しています。
- 「いづるや」: 池から鯉や鮒が出てくるようだなぁ。
宿場名「池鯉鮒(ちりふ)」を、「池(いけ)」「鯉(こい)」「鮒(ふな)」という三つの言葉に分解し、そのまま歌に詠み込んでいます。
全体の意訳
春の夕風が吹いているものだから、たなびいていた霞の網が破れて、いまにも池から鯉や鮒が出てきそうだ。ああ、それもそのはず、ここはその名も「池鯉鮒」の宿なのだから。
鳴海から庄野まで
なるみ(鳴海)
きえのこる 雪も所の 名物と
かのこしぼりに なるみてふ宿
花岳春也
春になってもまだ消え残っている雪。地面に点々と残っている雪の様子です。
- 意味1(名物): 鳴海宿は「有松・鳴海絞(ありまつ・なるみしぼり)」という絞り染め(染物)の一大産地として全国的に有名でした。その中でも「鹿の子絞り(かのこしぼり)」は、絞り染めの代表的な模様です。
- 意味2(情景): 地面に点々と消え残る雪の様子が、まるで鹿の子供の背中の斑点模様、すなわち「鹿の子(かのこ)模様」のように見えること。
- 「なるみてふ宿」: 鳴海という宿。
- 「(かのこしぼりに)なる」: 鹿の子絞りの模様に成る。
全体の意訳
春になってもまだ消え残っている雪が、地面に点々と斑点模様を描いている。その景色は、まるでこの土地の名物のようだ。それもそのはず、ここは「鹿の子絞り」の模様で有名な有松・鳴海絞の産地「鳴海」の宿。この残雪は、まるで名物の絞り染めが地面に模様を成しているかのようにも見えることだなぁ。
みや(宮)
治まれる 御代には武士も やり梅の
みやあぶなしと さや廻りしつ
雪ノ降時
- 「やり」: 武器の槍、武士の縁語。
- 「やり梅」: ウメの一品種。花は白く、やや淡紅色を帯びる。
「やり梅」は「槍」という言葉を自然に(ダジャレとして)登場させるための道具にすぎないので、訳出する必要はありません。そのまま「槍」と言うと面白くないので、「やり梅」という言葉の中に「やり」を隠しているわけです。
- 「宮あぶなし」: 宮宿から桑名宿へは七里の渡しに乗るのが一般的ですが、荒天で渡海できないとき、宮から陸路で佐屋を経由する遠回りの道をとることがありました。佐屋から桑名までは川船で下ります。ここでは「宮から乗るのは危ない」という意味。
- 「鞘」: 鞘は武士の縁語。
- 「佐屋廻り」: 宮宿から桑名宿への迂回路を指す。(参考:佐屋回り)
全体の意訳
天下泰平のこの御時世だから、さすがの武士たちも、もはや槍を構えて戦うようなことはせず、宮からの渡し船に乗るのも危ないと避けて、佐屋街道の方へ回っていくことだよ。
桑名
たび人も けふは七里の 海の上
くわなくわたる 春のうららか
泉水亭庭守
宮宿から桑名宿までは「七里の渡し(しちりのわたし)」を船で渡る必要がありました。(参考)
- 意味1(地名): 桑名の宿へ渡る。
- 意味2(情景): 隈(くま)なく晴れ渡る。「隈なく」は「かげ・曇りがなく、はっきりと」という意味です。
全体の意訳
旅人たちも、今日はあの七里の渡しで船の上。一点の曇りもなく晴れ渡る良き日に、桑名の宿へ無事渡っている、春のうららかな日であることだなぁ。
四日市
こはあめに 舎るも三日 四日市
いつか都の 春に逢うべき
升廼屋千代丸
- 「強雨(こはあめ)」: ひどい雨、きびしい雨。
- 「四日市」: 宿場名。
前の句の「三日」と、地名の「四日(よっか)市」が、数字の続きとして配置されています。
- 「何時(いつ)か」: いったいいつになったら。
- 「五日(いつか)」: 「三日」「四日」と続いた数字の、次に来る「五日」。
全体の意訳
このひどい雨のせいで、この宿に泊まるのも、もう「三日」目。ここは「四日市」という宿だが、このままだと明日(「五日」目)も足止めだろうか。いったい「いつ」になったら、私は都の春に逢うことができるのだろう。
石やくし(石薬師)
咲うめの かなぶつならで うぐいすの
きて経をよむ いし薬師堂
ナルト 花王軒芳住
宿場の名前の由来である石薬師寺のこと。この寺は、立派な金属製の仏像ではなく、弘法大師が地面生え抜きの石に刻んだ石仏を薬師如来(石薬師)として祀っていることで有名です。
- 「金仏」: ①金属、主に銅で作られた仏像のこと。②感情の乏しい人のたとえ。
- 意味1(仏像の種類): 金属で作られた仏像ではなくて。
- 意味2(読経者): 感情の乏しい僧侶ではなくて。
- 「うぐいす」: 春の鳥。一句目の梅との組み合わせで「梅に鶯」という定番表現が完成します。
- 「経をよむ」: 鶯の鳴き声「ホーホケキョ」をお経の「法華経」を詠んでいることに見立てた、和歌の伝統的な言葉遊びです。
全体の意訳
咲いている梅の木に、金仏のような感情の乏しい僧侶ではなくて、鶯がやって来て、まるで「法華経」のお経をあげているかのように美しく鳴いている。それもそのはず、ここ石薬師堂は金仏ではなくて、石仏を祀っているお堂だから、読経ですらも風流になるのだなぁ。
庄野
宿の名の しょうのにまさる 匂いかな
そよふく風の さそう梅が香
面也
- 「庄野」: 宿場名。
- 「樟脳(しょうのう)」: クスノキの精油の主成分。ハッカのようなスーッとする特有の清涼感のある香りを持ちます。古くから衣類の防虫剤として使われてきました。
全体の意訳
この庄野の宿に漂う香りは、なんと素晴らしい匂いだろう。ここ庄野宿の名に似た「樟脳」にも勝るほどだ。それもそのはず、この匂いはそよ風が誘って運んできた梅の香りなのだから。
亀山から水口まで
亀山
旅人の 多き春とて 七ツ起
六ツをかくさぬ 亀山の宿
嵐山亭吹雪
春はお伊勢参りなどのシーズンで、旅人が非常に多い季節です。
- 「七ツ時」: 江戸時代の時刻で早朝の4時頃を指します。
- 地名「亀山」: その名の通り「亀」を強く連想させます。
- 亀の習性: 亀という生き物は、甲羅に「六つ」(=頭、尾、四本の足)を「隠す」ものです。
- 宿の情景: しかし、ここは「亀」山という名の宿なのに、慌ただしい旅人たちは、亀とは正反対です。
朝4時(七ツ時)という早朝に慌てて起きる旅人たちは、寝ぼけて布団から手足(=六つ)を「隠す」間もなく、バタバタと起きだしている、という意味になります。
全体の意訳
春はお伊勢参りのシーズンで旅人がごった返している。ここ亀山の宿では、皆が朝の4時(七ツ時)という早朝から起きだして大慌てだ。 ここは「亀」山という名の宿で、亀なら頭や手足など「六つ」のものを甲羅に「隠す」はずなのに、ここの旅人たちは(亀とは裏腹に)「六つ」(手足)を隠す(布団にくるまっている)間もなく、慌ただしく出発していくことだなぁ。
せき(関)
春くれば 関の地蔵の あたりまで
ふどしのように ひく霞かな
貫道
関宿の中央部に位置する関地蔵院にある地蔵。この地蔵には一休和尚との逸話が残っており、その逸話のなかでは最終的にお地蔵さんの首に一休和尚のふんどしをかけることで、騒ぎが収まったとのことです。関の地蔵とふんどしは切っても切れない関係にあります。(参考:関の地蔵と一休和尚)
- 「ふどし」: 褌(ふんどし)。
春霞が白く・長く、帯のようにたなびいている様子を「褌」の形状に見立てています。
全体の意訳
春がやって来ると、ここ関宿の地蔵院にある地蔵のあたりまで、見事に霞がたなびいている。その様は、あの地蔵の首にかけた一休和尚の「ふんどし」そのもののように白く長々とたなびいていることだなぁ。
坂の下
鶏の さかの下とて 春の日の
七ツ時より とまる旅人
百六齋大浦
- 「坂の下」: 宿場名。
この宿場は、東海道の難所の一つである鈴鹿峠のまさに坂の下(=ふもと)に位置していました。
- 「七ツ時」: 江戸時代の時刻で、夕方の4時頃を指します。
春は日も長くなっているのに、旅人たちは夕方4時頃という、まだ日の高い早い時間から宿に泊まっています。なぜなら、目の前に難所の鈴鹿峠が控えているため、この時刻から峠越えに挑むのは危険であり、ふもとである坂の下で一泊し、翌朝に備えるのが当然だったからです。
- 「鶏」: 鶏は七ツ時(夕方4時頃)になると、早々と寝床につく習性があります。
つまり、この歌は坂の下(峠のふもと)だからという理由で、早い時間(七ツ時)から宿に泊まる旅人たちの姿を、早寝の鶏になぞらえているわけです。
全体の意訳
ここは鈴鹿峠の「坂の下」という宿場だから、峠越えに備えて旅人たちは皆、まだ日も高い春の夕方4時頃(七ツ時)という早い時間から宿に泊まっている。 ――ああ、その姿はまるで、夕方になると早々と寝床につく鶏のようでもあることだなぁ。
解読者コメント
「七ツ時は朝と暮の二回ある。もしかすると、朝の4時ごろに鶏が鳴きだすことに掛けているのではないだろうか。また、鶏の「とさか」と「さか」を掛けていないだろうか?」とのご指摘がありました。うまくまとめられそうでしたら、別の解釈として解説を立てます。(朝の4時説をうまくまとめる方法など思いつきましたら、コメントいただければ幸いです)
土山
春雨の ふる土山を 大名の
けふをはれとて かざる宿入
楓枝園月人
土山宿の付近は雨が多いとされています。鈴鹿馬子唄に「坂は照る照る 鈴鹿は曇る あいの土山 雨が降る」と歌われており、この意味は「坂(坂下宿)は晴れ、鈴鹿(鈴鹿峠)は曇り、相対する土山(土山宿)は雨が降る」と解釈されることが多くて、鈴鹿峠を境に伊勢側と近江側では天候ががらりと変わるようです。
なお、土山は江戸時代に三回、大嘗会和歌の歌枕として詠進されています。いずれも別格の稲舂歌が詠まれており、土山には慶祝性があると見なされていた可能性があります。(参考:土山宿)
- 「ハレとて」: 特別な行事の日としての「ハレ」。普段を表す「ケ」に対する「ハレの日」。晴れの舞台。
雨が降っている(天気は晴れていない)のに、儀式としては「ハレ」の場である、という対比です。
- 「飾る」: 儀式(=ハレ)の宿入りなので、行列は威儀を正して立派に飾っています。
全体の意訳
春雨がしとしとと降っている、ここ土山の宿を、大名行列が進んでいく。 たとえ雨が降っていて晴れていなくとも、今日の宿入りは儀礼的な「ハレの日」の行事だということで、立派に飾った行列が宿に入っていくことだなぁ。
水口
おじゃれ女が はるの道者に つく嘘の
だれも一ぱい くう鰌じる
五ツ島人
- 「おじゃれ女」: おじゃれは「おいであれ」という呼びこみ言葉。おじゃれ女とは、宿場(茶屋や宿屋)の飯盛女や客引きの女性たちのことです。
- 「道者」: ここでは、連れ立って社寺を参詣・巡拝する旅人の意味。元は道教を修めた者、道士。
- 意味1: 誰も彼もが一杯食わされて(まんまと騙されて)。
- 意味2: 誰も彼もが(水口宿の名物である)どじょう汁を1杯食べている。
全体の意訳
呼び込みをする女(おじゃれ女)が、春の参拝(お伊勢参り)に行き交う旅人に対して
「ちょいとお兄さん寄っておいきよ」と(あたかも娼婦のように)誘う嘘に、誰も彼もが一杯食わされて(まんまと騙されて)、(水口宿の名物である)どじょう汁を1杯食べていることだなぁ。
解読者コメント
わざわざ「道者」という言葉を使っていることから、もしかすると中国の長編小説『紅楼夢』を下地にしているかもしれない、という指摘を頂いています。
石部から京都まで
石部
佐用姫の 如くこがれて 己が身も
石部の野辺に 妻乞るきじ
ナルト 梅泉亭澄男
日本の古い伝説の女性、松浦佐用姫。夫(大伴狭手彦)が朝鮮半島へ旅立つのを悲しみ、鏡山の頂から領巾(ひれ)を振って見送り、あまりの悲しみに「石」になってしまったとされます。
- 「石部」: 宿場名。
- 「己が身も 石」: 自分の身も「石」になる。佐用姫が夫を恋い焦がれて「石」になった伝説を踏まえる。
- 「雉」: 春になると雄の雉は、妻(雌)を求めて「けん、けん」と激しく鳴きます。
全体の意訳
春の野で、妻(雌)を求めて激しく鳴いている雉がいる。その姿は、まるで夫を恋い焦がれて、ついには「石」になってしまったという、あの佐用姫のようだ。あんなに激しく鳴いていたら、あの雉も佐用姫のように自分の身が「石」になってしまうのではないか。 ――それもそのはず、ここは「石」の名を持つ「石部」の野辺なのだから。
草津
七草の くさつの宿は 出女の
口をたゝきて とめる旅人
月人
「七草」は「草津」を導くための枕詞的な表現です。
宿屋や茶屋で働く客引きの女性のことだが、売春もした。飯盛女のこと。
- 「口を叩く」: 出女たちが、旅人を引き留めようと口早にしゃべりたてる(おしゃべりする、客引きをする)様子。
- 「(七草を)叩く」: 新年に七草粥を作るとき、特定の囃子ことばを唱えながら、七草を包丁などで叩く「七草叩き」という風習がありました。(参考:七草をたたきながら唱え事をする)
全体の意訳
正月の七草叩きで、囃子ことばを唱えながら七草を「叩く」あのやかましい声や音のように、ここ草津の宿では、出女たちが客引きのためにやかましく口を「叩いて」、旅人を宿に強引に引き止めていることだなぁ。
大津
うららかな 春は霞も ふた筋に
大津八丁 ひく車道
洒落齋起名
霞が「二筋」になる理由は、後述の「車道(くるまみち)」の二本の轍の「筋」と同じように、春霞の「筋」を見立てているためです。
- 「大津八丁」: 大津宿の中心部の約八丁(約870m)続く賑やかな道筋のこと。
- 「車道」: 大津の港に荷揚げされた米などの物資を都へ輸送する荷車の通行を楽にするために、花崗岩の車石を2列に敷き詰めた車道がありました。(参考)
- 「大八車」: 荷物の輸送に使われていた総木製の人力荷車。「大津八丁 ひく車道」のなかに「大八車」の文字が埋め込まれています。
- 「ひく車道」: 掛け詞になっています。
- 「(荷車を)引く」: 荷を積んだ荷車を「引く」車道。
- 「(春霞が)引く」: 春霞が長く「引く(たなびく)」。
全体の意訳
うららかな春の日だ。空には春霞が見事に「二筋」にたなびいている。その霞の「引きっぷり」は、まるで大津八丁にある「二筋」の車石を敷き詰めた「車道」のうえを、その名も大津八丁の車道にぴったりの大八車を「引いて」いく姿そっくりであることだなぁ。
大津絵の 鬼の念仏に ひきかえて
法華経をよむ 春のうぐいす
万戸楼千門
- 「大津絵」: 大津宿の名産品である民俗画。
- 「鬼の念仏」: 大津絵の代表的な画題の一つ。鬼が僧侶の姿をして念仏を唱えている図で、「見かけは立派でも内心は邪悪である」という偽善者を風刺したものです。
つまり、これは「偽物の念仏」の象徴です。
- 「法華経をよむ」: うぐいすの鳴き声「ホーホケキョ」を、お経の「法華経(ほけきょう)」を詠んでいることに「見立てた」、和歌の伝統的な言葉遊びです。
つまり、こちらは「本物の法華経」の象徴です。
全体の意訳
ここ大津宿は、名物の「大津絵」に描かれた「鬼の念仏」が有名だが、あれは鬼が唱えているので「偽物の念仏」だ。一方、それとは対照的に、外では春のうぐいすが、まるで「本物の法華経」を詠むかのように「ホーホケキョ」と美しく鳴いていることだなぁ。
ひきはへし 霞のまくに 大津なる
あれしみやこの しかもかくしつ
彩雲楼龍鳴
- 「ひきはへし」: 長く引きのばした。引き延ふ(ひきはふ)の活用形。
- 「霞の幕に」: 春霞がまるで幕のようになっている。
宿場町と琵琶湖の物資が集散する港町の機能を併せ持った大津宿は、江戸・日本橋から京都・三条大橋を結ぶ東海道五十三次の53番目の宿場で、全ての宿場の中でも最大の人口を有し、大変賑っていました。(参考)
- 「荒れし都の志賀」: 志賀の都とは飛鳥時代に天智天皇が近江国滋賀郡に営んだ都。近江大津宮とも呼ぶ。この都は天智天皇の死後、わずか5年余りで勃発した壬申の乱によって戦火に焼かれ、短期間で廃都となった。「大津」と言えば、平安時代以降の和歌の世界において「はかなく滅びた都」「繁栄と没落の象徴」として、一貫して感傷的かつ無常観を伴う歌枕として使われてきました。
- 「然も隠しつ(しかもかくしつ)」: そんなにまでも隠してしまった(「つ」は完了)。(参考:然も)
- 「しかも隠すか」: 大津といえば「額田王」、額田王が歌った「三輪山をしかも隠すか雲だにも心あらなも隠さふべしや」(参考)にある「しかも隠すか」を意識した表現と思われます。
全体の意訳
ここ大津の宿は、まるで長い幕を引いたかのように、春霞が一面に立ちこめている。——ああ、あの荒れ果てた「志賀」の都を、霞は「しかも(=まあ、これほどまでも見事に)」隠してしまったことだなぁ。(荒れ果てたかつての都の姿がまったく見えないほど、大いに栄えている大津の宿であることよ。)
京
さほ姫も 京女には はづかしと
霞の衣を かづきてやくる
六々園
佐保姫(さほひめ)は春を司る女神のこと。春の美しい景色(霞、花など)は、すべて佐保姫がもたらすものとされています。
- 「京女」: 京の都の女性。当時から、その美しさ、優雅さ、洗練された物腰やファッション(京友禅など)で日本一とされていました。
- 「はづかしと」: 恥ずかしいと思って。
- 「霞の衣」: 春の訪れとともに現れる「霞」を、佐保姫の着ている「衣」に見立てています。
- 「かづきて」: 衣や布を頭からすっぽり被って。恥ずかしさから顔を隠す仕草です。(参考:かづく)
- 「かづきてやくる」: すっぽり被ってやってくることだなあ。(「や」は詠嘆、または疑問)
全体の意訳
ついに京の都に春がやって来た。しかし、春の美を司る女神である佐保姫ご自身も、ここ京の都の女性たちのあまりの美しさや優雅さには敵わないと恥ずかしく思われたようだ。その証拠に、京の都に立ち込めているあの美しい春霞は、佐保姫が恥ずかしさのあまり(顔を隠すために)頭からすっぽりと被っている「霞の衣」そのものなのだから。
人物誌
参考文献:岩村家文書『桜間狂歌集』(徳島の古文書を読む会一班 史料集13)
六暁園卯時
《通称》治兵衛 《屋号》播磨屋 《号》深雪庵卯時(しんせつあん うとき)
阿波国徳島城下新シ町(現・徳島市中通町)
文化・天保の頃、阿淡狂歌の盛行時の中心狂歌師。桜間の池の建碑を喜び、全国に呼びかけ、狂歌一万首を募集し、緑樹園元有に選を乞い、一千首の『桜間狂歌集』を天保9年(1838)刊行した。
一桂亭五百丈(いっけいてい いおたけ)
《通称》山下常助 《屋号》上郡屋
阿波国阿波郡市場町(現・徳島県阿波市市場町)
一松亭枝遊
《通称》山下善作 義高 《屋号》上郡屋
阿波国阿波郡市場町(現・徳島県阿波市市場町)
花王軒芳住(かおうけん よしすみ)
《通称》叶次(治) 質直 《屋号》桜屋
阿波国撫養斉田(現・徳島県鳴門市撫養町斎田)
柯撰堂五瓢
《通称》和三兵衛 《屋号》寉島屋
阿波国徳島城下新シ町(現・徳島市中通町)
九峯舎静
《通称》鎌田禎助
阿波国徳島城下佐古(現・徳島市佐古町)
泉水亭庭守(せんすいてい にわもり)
《通称》熊吉 《屋号》北地屋
阿波国徳島城下新シ町(現・徳島市中通町)
梅泉亭澄雄(ばいせんてい すみお)
《通称》嘉兵衛 《屋号》近江屋
阿波国撫養北町(現・徳島県鳴門市撫養町斎田)
百六斎大輔(ひゃくろくさい おおすけ)
《通称》惣助(惣兵衛) 《屋号》郡屋
阿波国徳島城下東船場(現・徳島市東船場町)
枇杷廼屋鈴成(びわのや すずなり)
《通称》熊沢与三兵衛 利久
阿波国徳島城下八百屋町(現・徳島市八百屋町および両国本町1~2丁目)
山辺ノ秋人(やまべの あきひと)
《通称》善兵衛 《屋号》大塚屋
阿波国撫養斉田(現・徳島県鳴門市撫養町斎田)
六柯園猿人(ろくかえん さるひと)
《通称》政五郎 《屋号》万屋
阿波国徳島城下西新町(現・徳島市西新町)
六々園春足(ろくろくえん はるたり)
天明2年(1782)1月7日~天保5年(1834)1月26日
《通称》遠藤宇治右衛門
《号》雲多楼鼻垂(うんたろう はなたれ) 紀抜足(きのぬけたり)
阿波国石井村(現・徳島県名西郡石井町)
藍商。
江戸八丁堀・武州八王子などに支店を持ち、常に江戸と阿波を往来していた。本居大平・同内遠に国学を、宿屋飯盛(石川雅望)に狂歌を学ぶ。大田南畝・中島棕隠・加納諸平・賀茂季鷹らとも親交があった。
六樹園飯盛(石川雅望)ともに『阿淡狂歌三十六歌撰(天保3年石原熊左衛門刊)』を撰。文化・文政期の阿波・淡路狂歌界の大御所的存在で、阿波国狂歌の興隆は春足の力によるところが大きい。
《著作》『吾嬬日記(文政7)』『桃太郎物語』『白痴物語(文政8刊)』『猿蟹ものがたり(天保元刊)』他。
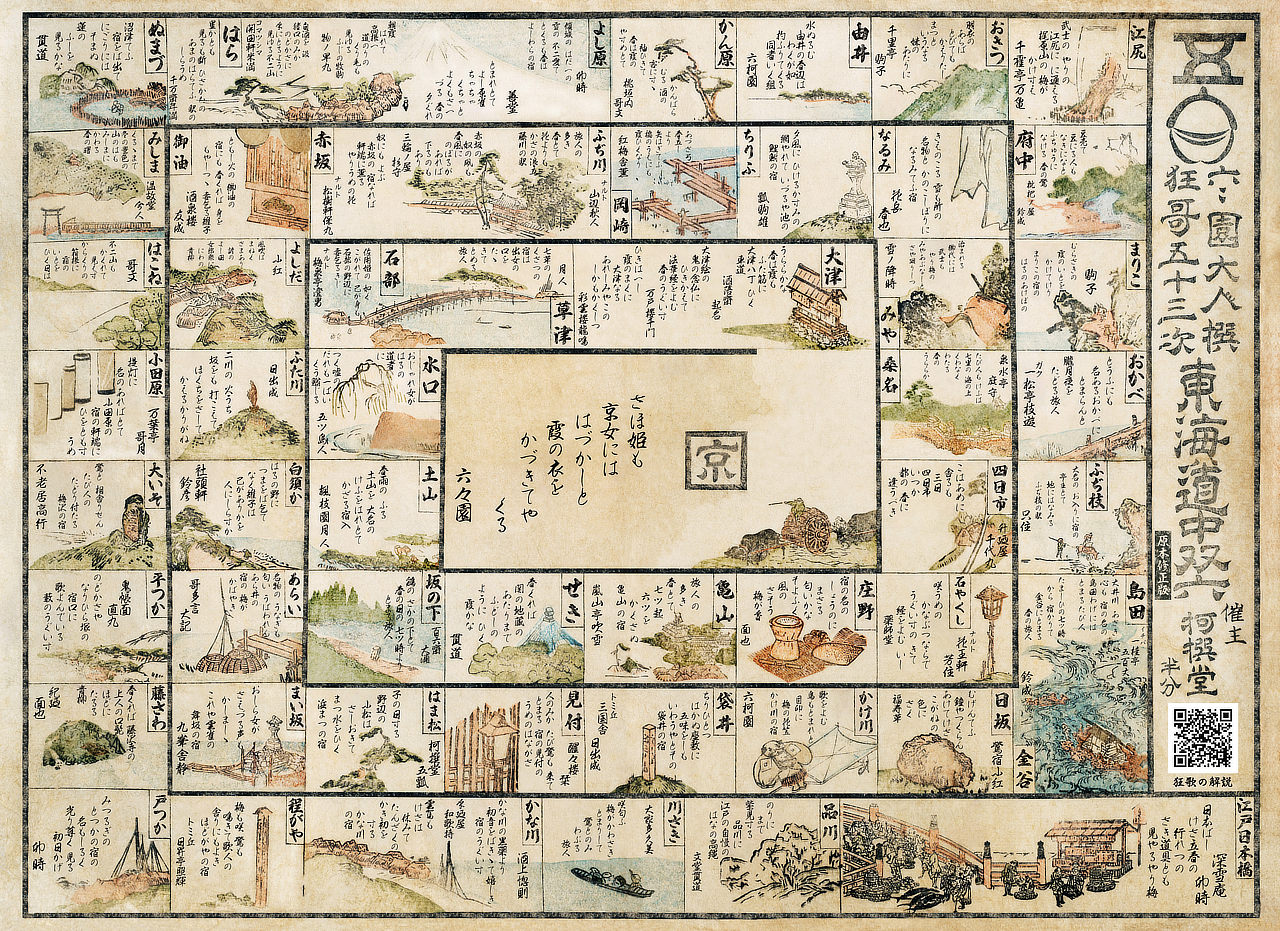


コメント