狂歌を作ってみようと思ったきっかけ
遠藤 今回は狂歌の創作について扱っていきたいと思います。抜六先生、よろしくお願いします。
抜六 はい、よろしくお願いします。しかし、遠藤さんには2年くらい前から狂歌づくりを持ちかけていましたが、どうして急に狂歌を作ってみようと思ったんですか?
遠藤 実は抜六先生以外に、親戚からも「それだけ狂歌の資料が残ってるなら、狂歌を作ってみたら?」って言われてたんですよね。ただ、これまでは、そうは言っても狂歌を作るのって敷居が高いなぁって思っていたんです。
書簡などの解読はちゃんと答えがある感じがしますけど、狂歌づくりは創作活動なので、正解がないじゃないですか。頭の使いどころがまったく違うってことで逃げ回っていたんですね。
ただ、最近になって徳島で活動されている『写楽の会』さんが狂歌コンテストを行うというニュースが流れてきまして…。見てみると、なんと賞金が大賞で5万円!これはもうやるしかないなって思って、意を決して狂歌を作ってみることにしたんです。
作ってみた狂歌
抜六 なるほど、そういうことだったんですね。
遠藤 はい、というわけでさっそく狂歌を作ってみました。
まだあがる? 株を買おうか 決めかねる
まだはもうなり もうはまだなり
2025年9月に日経平均株価が最高値を更新しましたよね。この歌は株価が高値圏にあるこのタイミングで株を買うべきかどうか決めかねている気持ちを表現しています。まだあがるって思う人が多ければ、もう天井に近いとか言うし、その逆もまた然り。そう考えると、どうにも決断できない優柔不断っぷりを歌っています。
ただ、これを狂歌って呼んでいいのかどうか正直悩ましいんですよね。私の理解では、狂歌は「縁語」「掛詞」「本歌取り」といったテクニックを使うものだと思っています。この歌には、そういった要素が入っていないので、単なる短歌なのでは?って不安になっているんです。
抜六 それは気にしないでいいですよ。私も狂歌を作るときには「縁語」「掛詞」「本歌取り」を意識しますが、出来上がったものがそれに沿っていないなんてことはしょっちゅうです。それでも、私の中では狂歌なので「狂歌」として出しています。あまり堅苦しく考えずに、どんどん自分が面白いと思うものを作っていって、そのうち狂歌らしいものが詠めることが増えていけばいいのですよ。
遠藤 そういうものなのですね。それを聞いて少し気が楽になりました。
狂歌を作るときの発想(遠藤版)
抜六 ところで、さきほどの狂歌はどういう発想で作ったのですか?
遠藤 最初に、ニュースで日経平均が最高値を更新したことを知ったので、株をテーマに狂歌を作ってみようと思いました。次に、表現として「うなぎのぼり」が思いついたので、うなぎに関係しそうな「ぬるぬる滑ってつかめない」を組み込んで、「上昇相場なのに、その波に乗れていない人」を表現してみようと思ったんです。
ただ、そこからがうまく5・7・5・7・7の音に落とし込めなくて…。2日ほど悶々としていたところに、別のニュースで「もうはまだなり」という表現を見かけました。調べてみると、「もうはまだなり まだはもうなり」という相場の格言だそうで、これを活かす方向で考えたら、あとはすんなり出てきましたね。
抜六先生のお返しの狂歌
抜六 なるほど。私が遠藤さんの狂歌から感じたのは「株でひと儲けしたい気持ち」です。それに対して、次のようなお返しの狂歌がぱっと思いつきました。
なれや知る 株価は野辺の 夕ひばり
上がるを見ても 落つる涙は
遠藤 えーと???これは本歌取りですか?
抜六 そうです。本歌は以下のものです。
汝や知る 都は野辺の 夕ひばり
あがるをみても 落つる涙は
飯尾彦六左衛門尉
(応仁の乱で焼け野原になってしまった京の都)
夕ひばりよ、お前は知っているか?
空高く舞い上がっていくお前の姿を見ていても
思わずこぼれ落ちてしまう私の涙を。
遠藤 !!! ということは、先生の狂歌は次のように解釈できるってことでしょうか?
汝や知る 株価は野辺の 夕ひばり
上がるを見ても 落つる涙は
夕ひばりよ、お前は知っているか?
世間では株価が上がっていくのに
思わずこぼれ落ちてしまう私の涙を。
つまり、株価が上がっても私は恩恵を得られていない。もっと言えば、本歌を踏まえると「私の財務状況は焼け野原状態である」ことを示唆していると想像できますね。
狂歌の解釈は違ってもいい
抜六 あはは、そう受け取りましたか。なるほど、この歌だけで考えればそうなりますね。
ただ、私は、遠藤さんの狂歌に対するお返しとして
・「あなたは知っていますか?」という意味の「汝(なれ)や知る」
・「上がる」「落ちる」の発想
この2つの要素から「あの歌があったなぁ」と「汝や知る 都は野辺の 夕ひばり…」の歌を思い出して、「都」を「株価」に変えてみたら、うまくハマったのでお出ししただけなんです。
つまり、私の返歌の意図は「遠藤さん、あなたは知っていますか?世間で株が上がる人もいれば、下がって涙を落とす人もいるんですよ」というものなのですよ。
遠藤 そうだったんですね。私の解釈もあり得るし、抜六先生の意図もわかる…。ということは、狂歌については解釈が違っていてもかまわないってことですか?
抜六 所詮は言葉遊びですからね。「こうも受け取れるし、ああも受け取れる。これは面白い歌だね」でいいと思います。
狂歌は言葉遊び
遠藤 しかし、これは本当に最小限の労力で最大限の効果を引き出している感じがしますね。
抜六 それが狂歌の面白いところですね。今回で言えば「みやこ」を「かぶか」に変えるだけで、全然意味が変わってしまう。そういう言葉遊びを楽しむのが狂歌の醍醐味です。
ただ、注意点として、本歌取りをするのであれば、みんなが知っているような歌を題材にしたほうがいいです。高校の教科書に載っているようなものに留めておくべきでしょうね。
遠藤 聞いた人がピンとくる必要がありますもんね。私はそのレベルの歌もおさえられていないのでお恥ずかしい限りですが、高校の教科書くらいであればそんなに時間がかからないと思うので、読み返しておこうと思います。
抜六 本歌取りの狂歌は狙って作れるようなものではないんですよ。縁のようなもので、ときたま降りてくるくらいです。私も普段作っているのは遠藤さんと同じような形式の歌です。あまり気張らずに、面白いフレーズを見つけたら5・7・5・7・7に整えてみるくらいの心持ちで取り組んでみてください。
遠藤 はい、りょうかいです。引き続き狂歌づくりに取り組んでいきます。今日はありがとうございました!


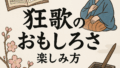

コメント